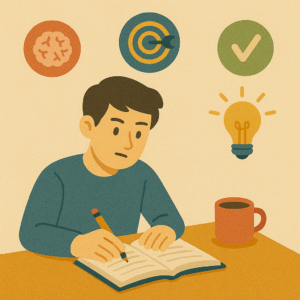集中力が低い人必見!集中力が続かない原因と維持する方法を解説
集中力とは?

集中力の意味と定義
集中力とは、特定の作業や目標に対して意識を持続させる能力のことです。勉強や仕事において、外部の雑音や気が散る要因に左右されず、一定の時間集中し続けることが求められます。
例えば、試験勉強の際にスマホの通知や周囲の音に気を取られずに勉強を続けられる人は集中力が高いといえます。一方で、すぐに他のことに気を取られてしまう人は、集中力が低い傾向にあります。
人間の集中力が持続する時間
人間の集中力には限界があり、長時間維持することは難しいとされています。以下のような研究結果があります。
・ポモドーロ・テクニック:25分間集中し、5分間休憩するサイクルを繰り返すことで、集中力を持続しやすくなるとされています。
・心理学者ジョン・スウェラー博士の研究:人間の集中力は最長でも90分程度が限界とされており、それ以上続けるとパフォーマンスが低下する可能性があります。
・マイクロソフトの調査:デジタル時代の影響により、人間の平均的な集中力は8秒にまで低下していると報告されています。
このように、人間の集中力は一定時間が経過すると自然に低下するため、適度な休憩を挟みながら作業を進めることが大切です。
集中力が続かないとどうなる?

仕事や勉強の効率が落ちる
集中力が続かないと、仕事や勉強の効率が大幅に低下します。例えば、1時間で終わるはずの作業が気が散ってしまうことで2〜3時間かかることもあります。これにより、業務の生産性が低下し、スケジュール管理が難しくなることもあります。
ケアレスミスが増える
集中力が低下すると、注意力が散漫になり、誤字脱字や計算ミス、作業の抜け漏れなどのケアレスミスが増えます。特に、細かい作業や確認作業を要する業務では、集中力の低下が大きな問題につながります。
モチベーションが低下する
集中できない状態が続くと、作業が思うように進まず「やる気が出ない」「成果が感じられない」といった状況に陥りやすくなります。このような状態が続くと、勉強や仕事に対する意欲が低下し、最終的には目標達成が難しくなることもあります。
このように、集中力の低下は生産性やミスの増加、モチベーションの低下など、さまざまな悪影響を及ぼすため、適切な対策を講じることが重要です。
集中力が続かない主な原因

睡眠不足や体調不良
集中力が続かない大きな要因のひとつが睡眠不足や体調不良です。睡眠が足りていないと、脳の働きが低下し、注意力や記憶力も衰えます。特に、睡眠時間が6時間未満になると、認知機能が著しく低下するという研究結果もあります。
睡眠不足の影響
・集中力の低下
・記憶力の低下
・判断ミスが増える
・眠気による作業効率の低下
厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針」によると、成人の推奨睡眠時間は7時間以上とされています。6時間未満の睡眠を続けると、注意力や判断力の低下を引き起こしやすくなると報告されています。
体調不良の影響
・頭痛や倦怠感により集中できない
・免疫力低下で病気になりやすく、継続的な作業が困難に
・体のだるさがやる気を削ぐ
栄養不足(脳のエネルギーが足りていない)
脳が正常に働くためには、適切な栄養補給が欠かせません。特にブドウ糖は脳の主要なエネルギー源であり、不足すると集中力が低下します。また、ビタミンB群や鉄分、オメガ3脂肪酸なども脳の働きを支える重要な栄養素です。
栄養不足による影響
・頭がぼーっとする
・集中力が続かない
・イライラしやすくなる
農林水産省の資料によると、バランスの取れた食事をすることで、脳の働きが向上し、集中力や記憶力が維持されることが確認されています。
集中力を維持するための栄養素と多く含む食品
・ブドウ糖:脳のエネルギー源。ごはん、パン、フルーツなど。
・ビタミンB群:神経伝達物質の生成。豚肉、納豆、卵など。
・オメガ3脂肪酸:脳機能をサポート。魚(サバ・イワシ)、クルミなど。
・鉄分:酸素の供給を促進。ほうれん草、赤身の肉など。
気が散る環境(騒音・スマホ・部屋の散らかり)
周囲の環境が整っていないと、集中力が持続しにくくなります。特に、スマートフォンやSNSの通知が頻繁に入ると、作業中に何度も意識が途切れ、集中が続かなくなります。
集中を妨げる環境要因
・騒音(テレビの音、話し声)
・スマホの通知(SNS・メッセージ・ニュース)
・部屋の散らかり(視界に余計な情報が入りやすい)
対策
・スマホをサイレントモードにする
・作業スペースを整理整頓する
・ノイズキャンセリングイヤホンを活用する
マルチタスクや「ながら作業」
一度に複数のことをこなそうとすると、注意が分散し、集中力が低下します。例えば「音楽を聴きながら勉強」「スマホを見ながら仕事」といったながら作業は、脳の処理能力を低下させる原因となります。
マルチタスクが集中力に及ぼす影響
・作業効率が30~40%低下する(スタンフォード大学の研究)
・記憶に残りにくくなる
・ミスが増えやすくなる
対策
・一つの作業に集中する「シングルタスク」を意識する
・集中時間を決め、短時間で効率よく取り組む
精神的なストレスや悩み
ストレスや不安があると、集中力を維持することが難しくなります。例えば、仕事のプレッシャーや人間関係の悩みがあると、気持ちがそちらに向いてしまい、作業に集中できなくなります。
ストレスが集中力を奪う理由
・ストレスホルモン「コルチゾール」が増加し、思考力が低下する
・不安が頭から離れず、作業に集中できない
・睡眠の質が低下し、疲れやすくなる
ストレス対策
・適度な運動を取り入れる(ウォーキングやストレッチ)
・瞑想や深呼吸をしてリラックスする
・仕事や勉強のスケジュールを見直し、無理をしない
作業が難しすぎる、または単純すぎる
作業が難しすぎるとストレスを感じ、逆に単純すぎると退屈になり、集中が続かなくなります。
難しすぎる作業の影響
・「自分には無理だ」と思い、やる気を失う
・疲れやストレスがたまりやすい
単純すぎる作業の影響
・退屈になり、気が散りやすい
・やる気が出ず、だらだらと作業してしまう
対策
・難しい作業は小さなステップに分ける
・単調な作業は制限時間を決めて取り組む
作業時間が長すぎる
長時間作業を続けると、脳が疲労し、集中力が維持できなくなります。特に、1時間以上を通しで作業するのは、集中力の低下を引き起こします。
作業時間と集中力の関係(研究データ)
・25分作業+5分休憩(ポモドーロ・テクニック)が最も効率的
・90分以上の連続作業は集中力が極端に低下する(心理学研究)
対策
・50分作業+10分休憩のルールを設ける
・作業の合間にストレッチや水分補給をする
このように、集中力が続かない原因はさまざまですが、対策を講じることで改善することが可能です。適切な休憩や作業環境の調整を行い、集中できる環境を整えていきましょう。
集中力を維持する方法・コツ

短い休憩を挟む(ポモドーロ・テクニック)
集中力を持続させるためには、適度な休憩が欠かせません。特に、ポモドーロ・テクニックは短時間集中と休憩を組み合わせることで、効率的に作業を進める方法として有名です。
ポモドーロ・テクニックの基本ルール
1.25分間集中して作業する
2.5分間休憩を取る
3.これを4セット繰り返した後に、15〜30分の長めの休憩を取る
心理学の研究では、人間の集中力は25〜45分がピークであり、それを超えると急激に低下すると報告されています(K. Anders Ericsson、研究論文)。
実践ポイント
・タイマーをセットして作業する
・短時間の目標を設定する(例:「25分でこのページを仕上げる」)
・休憩時間にスマホを触らない(脳をリセットするため)
仮眠をとる
短時間の仮眠は、集中力を回復させるのに効果的です。特に、15〜20分の仮眠(パワーナップ)を取ることで、頭がスッキリし、作業の効率が向上します。
仮眠のメリット
・脳の疲労回復
・記憶力・判断力の向上
・ストレス軽減
NASAの研究によると、26分の仮眠を取ることでパイロットの作業効率が34%向上したと報告されています。
実践ポイント
・昼過ぎ(13〜15時)の間に仮眠を取る
・15〜20分以内に抑える(30分以上は逆効果)
・仮眠後はコーヒーや軽い運動でスッキリ目覚める
生活習慣を見直す(睡眠・食事・運動)
集中力を維持するためには、日々の生活習慣が重要です。特に、質の良い睡眠・栄養バランスの取れた食事・適度な運動を意識することで、脳の働きが最適化されます。
良い生活習慣のポイント
・睡眠:7時間以上の睡眠を確保し、寝る前のスマホ使用を控える
・食事:脳に必要なブドウ糖・鉄分・オメガ3脂肪酸を意識して摂取する
・運動:1日20分のウォーキングやストレッチで脳の血流を促進する
実践ポイント
・寝る90分前に入浴してリラックスする
・朝食にナッツやフルーツを取り入れる
・作業前に軽くストレッチをして血流を良くする
作業環境を整える(デスク周りの整理・音・照明)
作業環境が集中力に大きく影響を与えます。デスクが散らかっていたり、騒音が多かったりすると、意識が分散しやすくなります。
集中しやすい環境のポイント
・デスク周りを整理整頓(必要ないものは片付ける)
・照明は明るめにする(青白い光は集中力を高める)
・ノイズキャンセリングイヤホンを活用する(カフェや図書館の環境音も有効)
実践ポイント
・作業開始前にデスクを片付ける
・スマホを視界に入れない場所に置く
・BGMを流す場合は、歌詞のないインストゥルメンタルを選ぶ
タスクを細かく分解してスケジュールを立てる
作業量が多すぎると、どこから手をつければいいかわからず、集中しにくくなります。そのため、タスクを細かく分解し、優先順位を決めて取り組むことが大切です。
効果的なタスク管理の方法
1.やるべきことをリスト化する
2.優先順位をつける(重要度・緊急度で分類)
3.1つのタスクは30分以内に終わる単位にする
実践ポイント
・「今日やること」を3つに絞る
・スケジュールは手帳やアプリで管理する(Googleカレンダーなど)
・朝一番に最も重要なタスクを終わらせる
集中力を高めるトレーニングを行う
集中力はトレーニングによって向上させることができます。特に、マインドフルネスやブレインゲームを活用すると、集中力の持続時間が長くなるとされています。
集中力向上トレーニングの例
・マインドフルネス瞑想(1日10分、呼吸に集中する)
・ビジュアルゲーム(記憶力を使うパズルやチェス)
・速読練習(本を速く読むことで脳の処理能力を鍛える)
実践ポイント
・朝起きたら5分間の深呼吸をする
・毎日10分間の瞑想を習慣化する
・頭を使うゲームやパズルを楽しむ
適度なリフレッシュや気分転換をする
長時間の作業を続けると、脳が疲れて集中力が落ちてしまいます。そのため、定期的にリフレッシュすることで、作業効率を維持できます。
おすすめの気分転換方法
・散歩やストレッチをする(外の空気を吸うとリフレッシュできる)
・好きな音楽を聴く(リラックス効果のあるBGMを選ぶ)
・アロマやカフェインを活用する(集中力を高める香りや飲み物を取り入れる)
実践ポイント
・1時間ごとに3〜5分のリフレッシュタイムを設ける
・気分が乗らないときは場所を変えて作業する
・「これを終えたら〇〇しよう」とご褒美を設定する
集中力を維持するためには、環境を整えたり、短時間で区切って作業したりすることが大切です。日常の小さな工夫を取り入れながら、自分に合った方法を見つけていきましょう。
集中力が低い人の特徴

計画や段取りを立てるのが苦手
集中力が低い人の多くは、計画や段取りを立てるのが苦手です。やるべきことを整理できていないと、どこから手をつけるべきか迷い、気が散りやすくなります。
計画が苦手な人の特徴
・タスクの優先順位をつけられない
・行き当たりばったりで作業を進めてしまう
・時間管理ができず、締め切り直前に焦る
対策
・タスクをリスト化し、優先順位を決める(例: ToDoリストを活用)
・1日のスケジュールを朝のうちに立てる
・ポモドーロ・テクニックを取り入れ、時間を区切って作業する
飽きっぽくすぐに気が散る
飽きっぽい性格の人は、作業を始めてもすぐに別のことに意識が向き、集中が続きません。特に、単調な作業や興味のないタスクは、注意散漫になりやすい傾向があります。
気が散りやすい人の特徴
・新しいことに興味を持ちやすいが、すぐ飽きる
・途中でスマホやSNSを見てしまう
・他の人の会話や周囲の音に影響されやすい
対策
・環境を整え、気が散るものを遠ざける(スマホは手の届かない場所に置く)
・タスクを短時間に区切る(25分作業+5分休憩)
・作業ごとに小さなご褒美を設定し、モチベーションを維持する
マルチタスクをしがち
複数の作業を同時進行するマルチタスクは、一見効率的に見えますが、実際には脳の負担を増やし、集中力を低下させます。
マルチタスクの影響
・一つの作業にかかる時間が増える
・記憶に定着しにくくなる
・ストレスが溜まりやすく、疲れやすい
対策
・1つの作業に集中する「シングルタスク」を意識する
・タスクの切り替えは、短い休憩を挟んで行う
・1日の作業時間をブロック単位に分け、異なる作業を交互に行う
睡眠や体調管理ができていない
十分な睡眠を取れていないと、集中力が著しく低下します。また、食生活の乱れや運動不足も脳の働きを鈍らせる原因となります。
体調管理ができていない人の特徴
・睡眠時間が6時間未満で慢性的に眠い
・食事の時間が不規則で栄養が偏っている
・運動不足で血流が悪く、頭がスッキリしない
対策
・毎日7時間以上の睡眠を確保する
・朝食にバナナやナッツなど脳に良い食材を取り入れる
・1日10分の軽い運動(ストレッチ・ウォーキング)を習慣化する
仕事や勉強の優先順位を決められない
集中力が低い人は、タスクの優先順位を決めるのが苦手な傾向があります。やるべきことが多すぎると、何から手をつければいいのか分からず、結局何も進まないこともあります。
優先順位が決められない人の特徴
・重要な仕事よりも簡単な仕事を先にやってしまう
・同時にいろいろなことを考えてしまい、作業が進まない
・期限を後回しにして、直前になって焦る
対策
・重要度と緊急度でタスクを分類し、優先順位を決める(例:Eisenhowerマトリクスを活用)
・1日の目標を3つに絞り、最も重要なタスクから取り組む
・朝一番に「最も頭を使う作業」を終わらせる
集中力を高めるおすすめアイテム

タイマー(ポモドーロ用)
ポモドーロ・テクニックを実践するためのタイマーは、集中力を維持するのに役立ちます。作業時間と休憩時間を設定することで、メリハリをつけながら効率よく作業ができます。
おすすめの活用方法
・スマホのアプリを活用する(例: Forest, Focus To-Do)
・デスクに小型のタイマーを置き、視覚的に時間を意識する
ノイズキャンセリングイヤホン
周囲の雑音を遮断し、作業に没頭できるノイズキャンセリングイヤホンは、集中力アップに最適なアイテムです。特に、カフェやオフィスのような騒がしい環境で作業する際に有効です。
おすすめの活用方法
・自然音やホワイトノイズを流して集中しやすい環境を作る
・通勤中や移動中でも作業の質を向上させる
集中力を高めるアロマやBGM
香りや音楽を活用することで、リラックスしながら集中しやすい状態を作ることができます。
おすすめのアロマ
・ローズマリー(記憶力向上・集中力アップ)
・レモン(気分をリフレッシュ)
・ラベンダー(リラックス効果で作業前の不安を軽減)
おすすめのBGM
・クラシック音楽(モーツァルト効果)
・環境音(雨音・波の音)
・低周波のホワイトノイズ
適度な糖分(チョコレート・ナッツ)
脳が働くためには、適度な糖分補給が必要です。特にブドウ糖が豊富な食品を適量摂取すると、集中力を維持しやすくなります。
おすすめの食品
・ダークチョコレート(ポリフェノールが脳の血流を促進)
・ナッツ類(アーモンド・クルミ)(ビタミンEが脳の老化を防ぐ)
・バナナ(ブドウ糖+ビタミンB6で脳の活性化)
注意点
・糖分の摂りすぎは逆効果になるため、適量を守る
・砂糖が多く含まれる清涼飲料水は避ける
適切なアイテムを活用することで、集中力を効果的に高めることができます。自分に合った方法を見つけ、作業効率を向上させましょう。
集中力が続かないのは病気の可能性も?
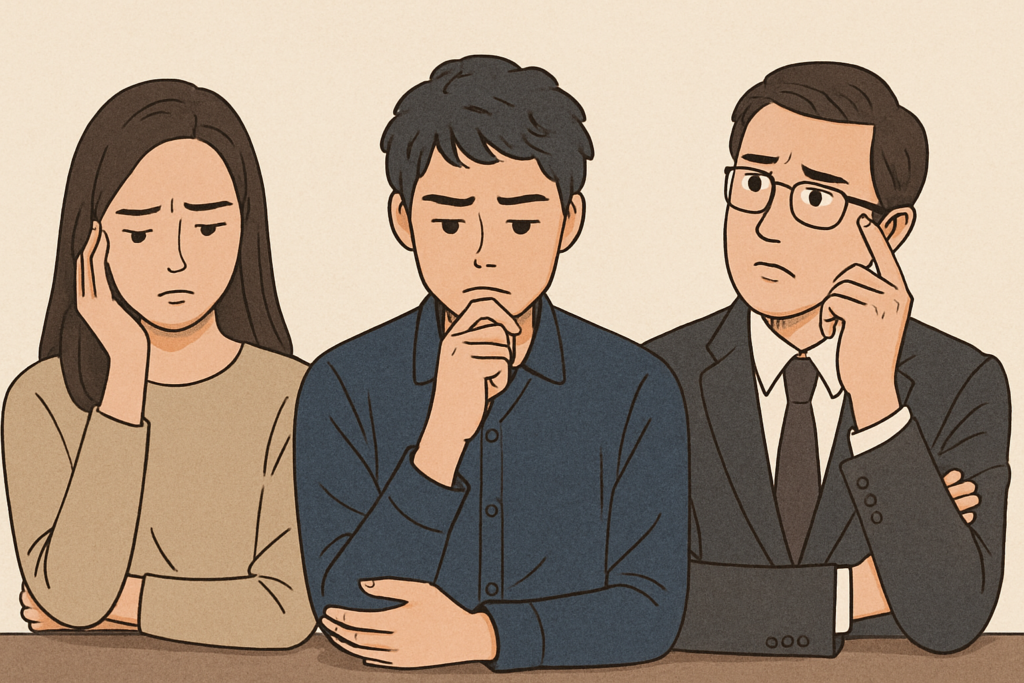
集中力が続かない原因は、生活習慣や環境の影響だけではなく、病気の症状として現れることもあります。特に、以下のような精神的・神経的な疾患は、集中力の低下と深く関係しています。
注意欠如・多動性障害(ADHD)
ADHD(注意欠如・多動性障害)は、注意を持続させることが困難になる発達障害の一つです。子どもの症状として知られていますが、大人になってからもADHDの特性が残ることがあり、仕事や日常生活に支障をきたすことがあります。
ADHDの主な症状
・注意が散漫になりやすい(話の途中で他のことを考えてしまう)
・マルチタスクが苦手(複数の作業を同時進行できない)
・衝動的な行動をとりやすい(思いついたことをすぐに行動に移してしまう)
・時間管理が難しい(締め切りを守れない、遅刻が多い)
厚生労働省の調査によると、日本におけるADHDの有病率は成人の約3~5%とされており、決して珍しい病気ではありません。
対策
・タスクを細かく区切り、短時間で終わる作業を繰り返す
・スケジュール管理アプリを活用し、時間管理を工夫する
・必要に応じて、医師に相談し適切な治療を受ける
うつ病・適応障害
気分の落ち込みやストレスが原因で、集中力が低下することがあります。特に、うつ病や適応障害では、脳の働きが鈍くなり、思考力や判断力が低下しやすくなります。
うつ病・適応障害の主な症状
・物事に興味が持てなくなる(何をするにもやる気が出ない)
・集中できず、作業を続けるのが困難になる
・疲れやすく、睡眠障害が生じる
・ネガティブな思考が止まらず、ストレスを感じやすい
WHO(世界保健機関)の報告によると、世界で約2億8000万人がうつ病を患っているとされ、日本国内では100人に6人の割合でうつ病の診断を受けた経験があるとされています。
対策
・規則正しい生活習慣を心がける(睡眠・食事・運動を意識する)
・過度なストレスを避け、適度にリラックスする時間を確保する
・カウンセリングや専門医の診察を受け、適切な治療を行う
統合失調症
統合失調症は、思考や認知に障害が生じる精神疾患です。症状の一つとして、注意力の低下や集中力の欠如が見られます。
統合失調症の主な症状
・思考がまとまらず、集中できない
・注意力が低下し、作業や会話がスムーズに進まない
・幻覚や妄想が生じることがある
・社会生活や日常生活が困難になる
統合失調症は、人口の約1%が発症するとされており、決して珍しい病気ではありません。早期の治療が重要で、適切な対応をすることで、社会復帰が可能になるケースも多いです。
対策
・病院で適切な診断を受けることが最優先
・生活リズムを整え、ストレスを最小限に抑える
・服薬治療を継続し、症状の管理を行う
集中力を高めるためのおすすめ書籍
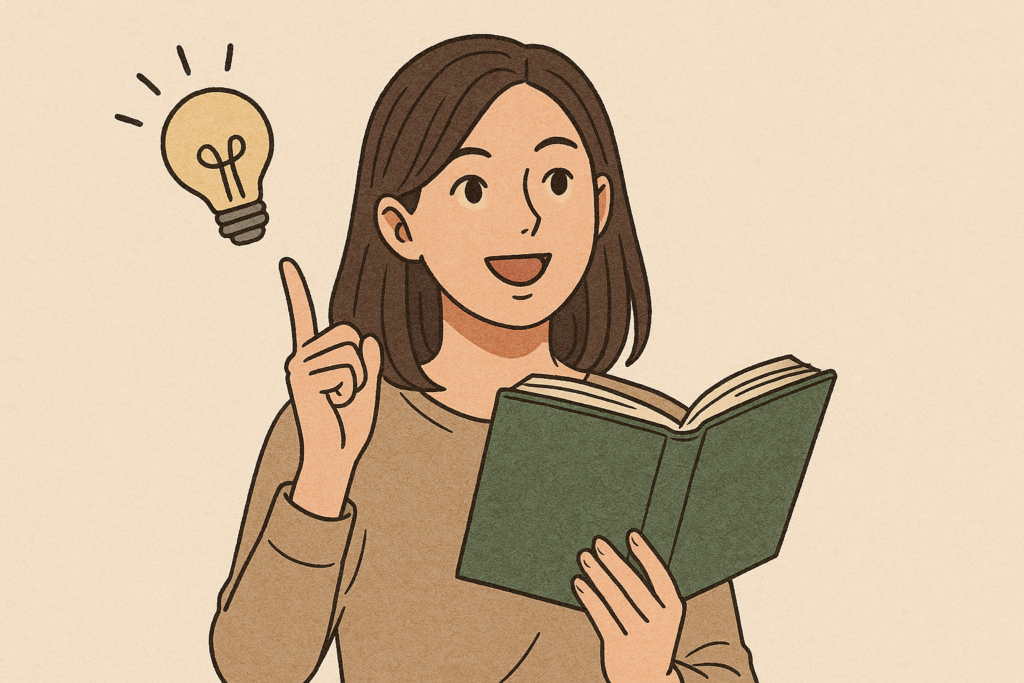
集中力を向上させるためには、正しい知識を身につけ、実践的な方法を学ぶことが大切です。ここでは、集中力に関するおすすめの書籍を3冊紹介します。
『ワン・シング 一点集中がもたらす驚きの効果』ゲアリー・ケラー著
この本では、「成功するためには、一つのことに集中することが重要である」という考えが提唱されています。マルチタスクではなく、シングルタスクに集中することで、成果を最大化できるという考え方が学べます。
この本から得られること
・何に集中すべきかを明確にする方法
・マルチタスクをやめ、シングルタスクに集中するメリット
・効率的に目標を達成するための具体的な戦略
おすすめポイント
・仕事や勉強の効率を上げたい人に最適
・シンプルで実践しやすい内容
『集中力 人生を決める最強の力』セロン・Q.デュモン著
本書では、集中力を鍛えるための具体的な方法や、脳の働きを最大限に活用するコツが紹介されています。
この本から得られること
・集中力の仕組みと、それを鍛える方法
・脳のパフォーマンスを向上させる思考習慣
・目標達成に必要なメンタルトレーニング
おすすめポイント
・心理学的な視点から集中力を解説
・実践的なトレーニング方法が豊富
『自分を操る超集中力』メンタリストDaiGo著
メンタリストDaiGo氏による、科学的根拠に基づいた集中力の向上方法が紹介されています。
この本から得られること
・集中力を高めるための習慣づくり
・気が散らない環境の作り方
・効果的な休憩の取り方と、脳のリフレッシュ方法
おすすめポイント
・日本人向けにわかりやすく書かれている
・すぐに実践できる方法が多い
集中力を維持するためには、病気の可能性を理解し、必要に応じて適切な対策を講じることが重要です。また、集中力を鍛えるための書籍を活用し、日常生活に役立つ知識を取り入れることで、より効率的に作業や勉強に取り組むことができるでしょう。
集中力を高めて効率的に行動しよう

今回は、集中力が続かない原因や、その維持方法について解説しました。
集中力が低下する主な原因には、睡眠不足や栄養不足、気が散る環境、ストレスなどが挙げられます。こうした要因を改善することで、集中力を向上させることが可能です。具体的には、ポモドーロ・テクニックを活用した休憩の取り方や、作業環境の整備、適切な生活習慣の見直しなどが効果的です。
集中力を維持できるようになると、仕事や勉強の効率が上がり、ストレスも軽減されます。今回紹介した方法をぜひ実践し、集中力を味方につけて充実した毎日を送りましょう!
投稿者プロフィール
最新の投稿
 お知らせ2025年5月16日保険の特約とは?初心者向け解説
お知らせ2025年5月16日保険の特約とは?初心者向け解説 お知らせ2025年5月16日学資保険おすすめランキングと選び方【初心者向けガイド】
お知らせ2025年5月16日学資保険おすすめランキングと選び方【初心者向けガイド】 マインド2025年5月16日自転車のヘルメット着用ガイド|法律・背景・選び方
マインド2025年5月16日自転車のヘルメット着用ガイド|法律・背景・選び方 マインド2025年5月16日自転車の「ながらスマホ」罰則強化と道路交通法改正【2024年11月施行】
マインド2025年5月16日自転車の「ながらスマホ」罰則強化と道路交通法改正【2024年11月施行】