学資保険の解約とは?リスクや返戻金、税金のすべてを解説
学資保険を解約しようか悩んでいませんか?

「途中で解約すると損をするって本当?」
「返戻金はいくら受け取れる?」
「税金や確定申告はどうなるの?」
そんな疑問や不安をお持ちの方も多いでしょう。
本記事では、学資保険の解約に関するリスク、返戻金の仕組み、税金の影響まで、初心者にもわかりやすく解説します。特に「解約で損をしないための対策」や「解約しなくても資金を確保する方法」も紹介するので、最適な判断ができるようになります。
本記事の情報は、保険業界の仕組みを熟知した専門的な知識をもとに執筆しています。実際に、多くの方がこの記事を読んで、学資保険の解約で後悔しないための適切な選択をしています。
この記事を最後まで読むことで、あなたにとって最も損のない方法を見極め、教育資金の準備を安心して進められるようになります。ぜひ最後までご覧ください!学資保険の解約とは?基礎知識と仕組み
学資保険の解約とは?基本的な仕組み
学資保険は、子どもの教育資金を計画的に準備するための貯蓄型保険です。契約者(親など)が保険料を支払い、契約期間が満了すると、設定した保険金を受け取ることができます。しかし、途中で解約すると、満期時に受け取れるはずの金額よりも少ない解約返戻金しか戻らない場合があります。
また、学資保険には「貯蓄型」と「保障型」の2種類があり、保障型の場合は生命保険の機能も兼ね備えています。そのため、解約すると教育資金だけでなく、保障も失う可能性があるのです。
解約のポイント
・学資保険は途中で解約すると元本割れすることが多い
・保障型の場合、契約者に万が一のことがあった際の保障もなくなる
・解約返戻金の有無や金額は契約内容によって異なる
途中解約はいつでも可能?解約のタイミング
学資保険は基本的に契約者の意思で解約できますが、解約のタイミングによって受け取れる金額が大きく変わります。特に、契約開始から数年以内に解約すると、支払った保険料よりも大幅に少ない額しか戻らないことが多いです。
解約のタイミングによる影響
・契約開始~数年以内:解約返戻金はほぼゼロ、または元本割れ
・契約期間の中盤:少しずつ解約返戻金が増えるが、元本割れの可能性あり
・契約期間終盤:多くのケースで支払額以上の解約返戻金を受け取れる
金融庁の報告によると、学資保険の解約返戻金は加入後10年未満の場合、支払った保険料の70~90%程度が戻るケースが多いとされています。ただし、契約内容によって異なるため、保険会社の公式情報を確認することが重要です。
学資保険を解約するとどうなる?解約リスクとデメリット

途中解約すると元本割れする可能性が高い
学資保険は長期契約が前提となっているため、途中解約すると元本割れするリスクが非常に高いです。これは、保険会社が保険運営のためのコストを差し引いた後に返戻金を計算するためです。
元本割れの例
・月1万円の保険料を5年間(計60万円)支払った場合
・5年目で解約すると、解約返戻金は40万円しか戻らない(20万円の損失)
・満期まで継続すれば、受け取れる総額は110万円
元本割れを防ぐには、解約前に解約返戻金の額を確認し、見直しの選択肢を検討することが大切です。
先払いした保険料が無駄になることもある
学資保険には、一括払いや年払いなどの支払い方法が選べる場合があります。しかし、途中解約すると、先払いした保険料の一部が戻らず損失となる可能性があります。
具体例
・10年契約の学資保険に加入し、5年分の保険料を一括で支払った
・5年後に解約した場合、本来の契約満了時に戻ってくるはずの返戻金が減る
・結果的に、一括払いのメリットを活かせず損をする
そのため、一括払いを選ぶ際は「途中解約時にどの程度返金されるか」を保険会社に確認しておきましょう。
保険の保障がなくなる
学資保険には「契約者(親)が死亡した場合、それ以降の保険料が免除される」という保障が付いていることが多いです。しかし、途中解約するとこの保障もなくなってしまいます。
保障が消失するリスク
・親が死亡しても学資保険金が受け取れなくなる
・教育資金の確保が難しくなる
・家計が厳しくなった場合、再度加入するのが難しくなる
このようなリスクを避けるため、学資保険の解約は慎重に検討する必要があります。
学資保険の再加入が難しくなる・再加入時の保険料が上がる
一度学資保険を解約してしまうと、再加入が難しくなる場合があります。また、再度加入できたとしても、契約時の年齢が高くなることで保険料が高くなる可能性があるのです。
学資保険の再加入に関する注意点
・加入時の年齢が上がると保険料が増加する
・一部の学資保険は、一定の年齢を超えると加入できない
・既往歴や健康状態によっては審査に通らない場合もある
そのため、解約する場合は「本当に再加入が必要にならないか」を慎重に検討しましょう。
教育資金の準備が不十分になるリスク
学資保険は、子どもの進学時に備えるための貯蓄手段の一つです。しかし、解約してしまうと計画していた教育資金の準備が難しくなることがあります。
教育資金不足の影響
・進学先の選択肢が狭まる
・奨学金や教育ローンの利用が必要になる
・生活費に影響を与える
解約する場合は、代わりとなる貯蓄手段を準備しておくことが重要です。例えば、定期預金や投資信託を活用する、教育ローンの活用を検討するなど、他の資金確保方法も考えておきましょう。
学資保険の解約は簡単に決められるものではなく、多くのリスクを伴います。特に、元本割れや保障の消失、教育資金不足などのデメリットがあるため、事前に十分な情報を収集し、慎重に判断しましょう。
学資保険を解約しないためにできること(見直し方法)
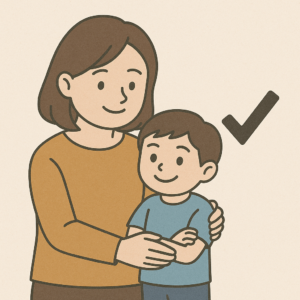
無理のない保険料の設定
学資保険を無理なく継続するためには、保険料の設定を適切にすることが重要です。契約時に収入と支出のバランスを考え、長期間にわたって支払い続けられる金額に設定しましょう。
適切な保険料の設定方法
・家計全体の支出を見直し、無理のない金額を設定する
・生活費や貯蓄とのバランスを考慮する
・収入が増えた場合、追加で貯蓄をするなど柔軟に対応
厚生労働省の調査によると、子ども1人あたりの教育費の平均は小学校から大学までで約1,000万円~2,500万円と言われています。学資保険だけで全額をカバーするのは難しいため、無理のない保険料で加入し、他の資産運用方法も併用することが賢明です。
契約者貸付制度を利用する
契約者貸付制度は、解約せずに学資保険を担保にお金を借りる方法です。学資保険の解約返戻金の一部を保険会社から借り入れることで、保険を維持しながら一時的な資金不足を補えます。
契約者貸付制度の特徴
・解約せずに資金を借りられる
・返済すれば保障や保険の継続が可能
・一定の金利が発生する
ただし、借入金を返済しないと最終的に解約返戻金が減る可能性があるため、利用する際は返済計画をしっかり立てましょう。
自動振替貸付制度を活用する
自動振替貸付制度は、保険料の支払いが一時的に困難になったときに、解約返戻金から自動的に保険料を立て替える仕組みです。
メリット
・一定期間、保険料の支払いを猶予できる
・保険を解約せずに維持できる
・追加の手続きが不要
デメリット
・立て替えられた金額に対して利息が発生する
・解約返戻金が減少する可能性がある
この制度を利用する場合、早めに家計の見直しを行い、保険料の支払いを再開できるようにすることが大切です。
払済保険に変更する
払済保険とは、今後の保険料の支払いを停止し、それまで支払った保険料に応じた保障を継続する方法です。
払済保険のメリット
・追加の保険料負担がなくなる
・解約するよりも元本割れのリスクを抑えられる
デメリット
・受け取れる保険金額が減る可能性がある
・契約によっては払済保険への変更ができない場合がある
学資保険を解約せずに維持する選択肢として、有効な方法の一つです。
一部解約(減額)を行う
保険料の負担を軽減するために、一部解約(減額)を行う方法もあります。これは、保険金額を減額することで、月々の保険料を抑える仕組みです。
一部解約のメリット
・保険を解約せずに維持できる
・保険料の負担を軽くできる
デメリット
・保険金額が減少する
・解約返戻金の計算が変わる場合がある
学資保険の継続を検討する際は、一部解約も有効な手段です。
特約を外して保障をシンプルにする
学資保険には、医療保障や育英年金などの特約が付帯している場合があります。特約を外すことで、月々の保険料を減らし、負担を軽減することが可能です。
特約を見直す際のポイント
・どの特約が本当に必要かを確認する
・特約を外した場合の影響をチェックする
特約を削ることで、本来の目的である「教育資金の確保」を優先し、無駄な出費を抑えることができます。
解約後に受け取れる返戻金の仕組み

解約返戻金とは?
学資保険を解約すると、解約返戻金が受け取れます。これは、保険料の一部が積み立てられており、解約時に払い戻されるお金です。
解約返戻金のポイント
・契約期間が長いほど返戻金が増える
・解約のタイミングによっては元本割れする
解約返戻率
解約返戻率は、支払った保険料に対してどれくらいの金額が返ってくるかを示す割合です。
計算式は解約返戻金÷払込保険料×100(%)となります。
一例
・支払った保険料の合計:100万円
・解約返戻金:80万円
・解約返戻率:80%
一般的に、契約期間が短いほど解約返戻率は低くなります。
返戻率をできるだけ高くするには?
解約返戻率を高くするためには、以下の方法を検討しましょう。
解約返戻率を上げる方法
・満期まで契約を継続する:満期前に解約すると元本割れする可能性が高い
・保険料の払い込みを早く終える:短期払いのほうが返戻率が高くなる場合がある
・祝い金を受け取らずに満期まで貯める:途中で祝い金を受け取ると返戻率が下がることがある
金融庁の調査によると、学資保険の返戻率は加入プランや支払い方法によって90~110%程度となるケースが多いです。
学資保険の解約を避けるための見直し方法を活用すれば、保険を維持しながら資金繰りを改善することができます。また、解約返戻金を最大限に活用する方法も理解し、計画的に対応することが重要です。
解約返戻金に関わる税金と確定申告の必要性
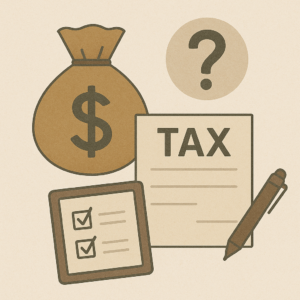
解約返戻金にかかる税金の種類(所得税・贈与税)
学資保険の解約返戻金には所得税または贈与税がかかる場合があります。課税対象となるかどうかは、契約者と受取人の関係によって決まります。
課税区分の違い
・契約者、受取人ともに親の場合:所得税(一時所得)
・契約者が親、受取人が子どもの場合:贈与税
所得税(一時所得)
・学資保険の契約者と解約返戻金の受取人が同じ場合、一時所得として課税されます。
・一時所得には特別控除(50万円)が適用され、控除後の金額の1/2が課税対象となります。
贈与税
・契約者と受取人が異なる場合、贈与税の対象となります。
・1年間の贈与額が110万円以下なら非課税ですが、それを超えると贈与税が発生します。
確定申告が必要な場合・不要な場合
確定申告が必要なケース
・解約返戻金が50万円の特別控除を超えた場合(所得税)
・1年間の贈与額が110万円を超えた場合(贈与税)
確定申告が不要なケース
・返戻金が特別控除(50万円)以内の場合
・契約者と受取人が異なり、贈与額が110万円以下の場合
生命保険料控除の対象になる?年末調整や確定申告の方法
学資保険の保険料は生命保険料控除の対象となる場合があります。年末調整や確定申告で控除を受けられるため、支払証明書を保管しておきましょう。
生命保険料控除の種類
・2012年1月1日以降の契約:新制度の生命保険料控除
・2011年12月31日以前の契約:旧制度の生命保険料控除
控除を受けるには、会社員の場合は年末調整で申告、個人事業主の場合は確定申告で申告する必要があります。
学資保険の解約手順

解約の流れと必要な手続き
学資保険を解約する際は、以下の手順を踏むことになります。
学資保険の解約手順
1.保険会社に解約の意思を伝える(電話または窓口)
2.必要書類を準備する(契約者の身分証明書、保険証券など)
3.書類を提出し、解約手続きを進める
4.解約返戻金を受け取る(指定口座へ振り込まれる)
解約のタイミングに注意!
解約のタイミングによって、受け取れる返戻金額が大きく異なります。
・契約から数年以内:元本割れが大きい(支払額の70%以下)
・契約期間の中盤:少しずつ返戻率が上がる
・満期直前:元本割れのリスクが低い
学資保険は満期に近づくほど返戻率が上がるため、できるだけ満期まで継続するのが理想です。
解約手続きの際の注意点
・保険料の未払いがあると解約時の返戻金が減る
・契約者が死亡している場合、解約手続きが複雑になる
・途中解約すると生命保険料控除の適用を受けられなくなることがある
解約する前にチェック!学資保険以外の資金準備方法
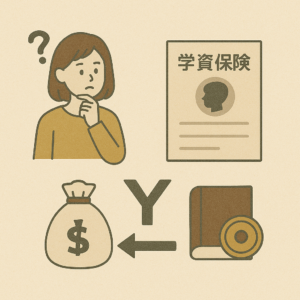
定期預金や別の貯蓄型保険を活用する
学資保険を解約せずに資金を確保する方法として、定期預金や他の貯蓄型保険を活用する手段があります。
定期預金の特徴
・解約しても元本割れしない
・必要な時にすぐ引き出せる
貯蓄型保険の特徴
・一定期間後に満期金が受け取れる
・保険としての保障も得られる
学資保険の解約を検討する前に、他の貯蓄手段との比較を行うことが大切です。
一時的な資金不足なら借入制度の利用も検討
一時的に資金が足りない場合は、借入制度を活用するのも選択肢の一つです。
利用できる借入制度
・契約者貸付制度(学資保険を担保にお金を借りる)
・公的機関の教育ローン(低金利で借りられる)
・金融機関のフリーローン(審査が必要)
借入制度を利用する場合は、返済計画をしっかり立て、利息負担を抑えることが重要です。
学資保険の解約には様々な影響があるため、解約する前に税金や確定申告の確認、資金調達の方法をしっかり検討することが大切です。
学資保険の解約は慎重に!最適な選択をするために
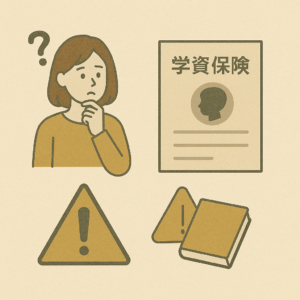
学資保険の解約には、元本割れのリスクや保障の消失、再加入の難しさなど多くのデメリットが伴います。しかし、契約者貸付制度や払済保険への変更など、解約を回避する方法も存在します。
また、どうしても解約する場合は、解約返戻金の計算方法や税金の影響を理解し、最適なタイミングで手続きを行うことが重要です。急いで解約せず、事前に資金準備の選択肢を検討しましょう。
学資保険は、お子さまの未来のための大切な資産です。この記事を参考に、解約が本当に最善の選択かどうか、慎重に判断してください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 お知らせ2025年5月16日保険の特約とは?初心者向け解説
お知らせ2025年5月16日保険の特約とは?初心者向け解説 お知らせ2025年5月16日学資保険おすすめランキングと選び方【初心者向けガイド】
お知らせ2025年5月16日学資保険おすすめランキングと選び方【初心者向けガイド】 マインド2025年5月16日自転車のヘルメット着用ガイド|法律・背景・選び方
マインド2025年5月16日自転車のヘルメット着用ガイド|法律・背景・選び方 マインド2025年5月16日自転車の「ながらスマホ」罰則強化と道路交通法改正【2024年11月施行】
マインド2025年5月16日自転車の「ながらスマホ」罰則強化と道路交通法改正【2024年11月施行】


