学資保険おすすめランキングと選び方【初心者向けガイド】
「学資保険って本当に必要?どれを選べばいいのかわからない…」
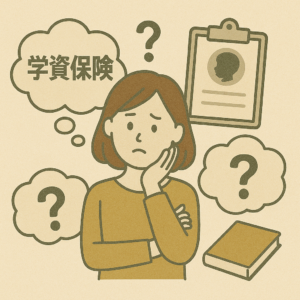
「返戻率が高いおすすめの学資保険が知りたい!」
こんなお悩みを解決します。
本記事では、学資保険の基本情報から選び方、おすすめランキングまで初心者にもわかりやすく解説します。さらに、返戻率を高めるコツや、学資保険以外の教育資金の準備方法についてもご紹介。この記事を読めば、自分に合った学資保険を選ぶための知識が身につき、将来の教育資金を安心して準備できるようになります。
金融や保険の専門知識をもとに、信頼性のある情報をお届けするので、ぜひ最後までチェックしてください!学資保険とは?基礎知識を解説
学資保険とは教育資金を準備するための保険
学資保険とは、子どもの将来の教育資金を計画的に準備するための保険です。主に大学進学時の学費として利用されることが多く、契約者(親や保護者)が一定期間保険料を支払い、満期時にまとまった保険金を受け取る仕組みになっています。
学資保険には、万が一の際の保障を重視する「保障型」と、資産形成を目的とした「貯蓄型」の2種類があります。保障型は契約者が死亡した場合、保険料の支払いが免除されるのが特徴ですが、貯蓄型は返戻率が高く、支払った金額以上の保険金を受け取れる可能性があります。
文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」によると、大学進学にかかる費用は私立大学で約400万円、公立大学でも約250万円となっています。このように高額な教育費を準備する手段として学資保険を活用する人が増えています。
例えば、Aさんは子どもが生まれた直後に学資保険(貯蓄型)に加入し、毎月1万円を積み立てました。その結果、満期時には約300万円を受け取ることができ、子どもの大学費用の一部として活用できました。
学資保険の2つのタイプ(保障型・貯蓄型)
学資保険には、次の2種類のタイプがあります。
1.保障型学資保険
・契約者(親)が死亡した場合、以降の保険料の支払いが免除される
・死亡保障が充実しているが、貯蓄性は低い
・保険金の受取額が支払総額より少ないことが多い
2.貯蓄型学資保険
・返戻率が高く、支払った保険料以上の金額を受け取れる可能性がある
・保障は少ないが、資産運用の一環として利用される
・途中解約すると元本割れするリスクがある
実例として、Bさんは「返戻率」を重視し、貯蓄型の学資保険を選びました。満期時には支払総額の110%の保険金を受け取ることができ、大学費用の資金として活用しました。
学資保険で受け取れるお金について
学資保険で受け取れるお金には、次の3つの種類があります。
1.満期保険金
・学資保険の契約期間が満了した際に受け取れるお金
・一括受取または分割受取を選択可能
2.祝い金(進学祝金)
・子どもが特定の年齢(中学・高校・大学入学時など)に達した際に支給されるお金
・支払い回数が増えると返戻率が低下する傾向がある
3.満期までの配当金(運用益)
・一部の保険では、運用実績に応じて配当金が支払われる場合がある
・貯蓄型の学資保険では、この配当金が返戻率の向上に寄与する
実例として、Cさんは祝い金が受け取れるタイプの学資保険を契約しました。子どもが高校入学時に50万円、大学入学時に100万円を受け取り、教育費の負担を軽減できました。
学資保険のメリット・デメリット

学資保険のメリット
計画的に教育資金を準備できる
学資保険を活用することで、毎月決まった額を積み立てる習慣ができ、計画的に教育資金を準備できます。特に、強制的に積み立てができるため、貯金が苦手な人にとって有効な手段です。
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査」によると、子どもの教育資金を「計画的に準備している」と回答した世帯のうち、約30%が学資保険を利用していると報告されています。
実例として、Dさんは貯金が苦手でしたが、学資保険に加入したことで毎月確実に積み立てができ、満期時には安心して子どもの大学費用を準備できました。
払い込んだ保険料以上の金額を受け取れる可能性
貯蓄型の学資保険では、返戻率が100%を超える商品もあり、払い込んだ保険料より多くの金額を受け取れる可能性があります。
例えば、Eさんは返戻率110%の学資保険に加入し、支払総額200万円に対して満期時に220万円を受け取りました。
生命保険料控除で節税できる
学資保険の保険料は、生命保険料控除の対象となるため、年間最大4万円の所得控除を受けられます。これにより、所得税や住民税を節税できるメリットがあります。
実例として、Fさんは生命保険料控除を活用し、年間で約1万円の税金を節約できました。
学資保険のデメリット
中途解約すると元本割れのリスクがある
学資保険は途中解約すると、支払った保険料よりも少ない金額しか戻ってこない可能性があります。
例えば、Gさんは子どもが10歳の時に学資保険を解約しましたが、返戻金は支払総額の80%ほどしか戻らず、損をしてしまいました。
お金を自由に引き出せない
学資保険は契約期間が決まっているため、満期前に自由にお金を引き出すことができません。急な出費が必要な場合、学資保険以外の資金準備も検討する必要があります。
実例として、Hさんは、急な医療費が必要になりましたが、学資保険から資金を引き出すことができず、別の貯蓄を活用せざるを得なくなりました。
インフレに弱い
学資保険は契約時に受取額が決まっているため、インフレが進んだ場合、実質的な受取額の価値が目減りする可能性があります。
実例として、Iさんは15年前に学資保険を契約し、満期時に300万円を受け取りましたが、物価の上昇により想定よりも学費が高くなってしまいました。
以上のように、学資保険にはメリットとデメリットがあるため、自身の目的に合った選択が重要です。
学資保険が不要な人・おすすめな人

学資保険をおすすめしない人の特徴
すでに教育資金の準備ができている
学資保険は教育資金を計画的に貯めるための手段ですが、すでに十分な貯蓄がある人にとっては必ずしも必要ではありません。たとえば、教育費のために十分な貯蓄があり、必要なタイミングで資金を確保できるのであれば、学資保険を契約するメリットは少なくなります。
例えば、Aさんは子どもが生まれた際にすでに500万円の教育資金を確保していたため、学資保険に加入する必要がありませんでした。代わりに、その資金を投資信託やNISAで運用し、さらに資産を増やす選択をしました。
保険料負担が厳しく、中途解約する可能性がある
学資保険は一定期間、決められた金額の保険料を支払い続ける必要があります。そのため、家計に余裕がない場合や収入が不安定な場合、中途解約をせざるを得ないケースがあります。しかし、中途解約すると元本割れのリスクが高くなります。
実例として、Bさんは子どもの将来のために学資保険に加入しましたが、家計の収支が厳しくなり途中解約しました。その結果、支払った保険料の70%ほどしか戻ってこず、損をしてしまいました。
自由に資産運用したい
学資保険は、契約時に決められた方法でしか資金を受け取れず、途中で自由に使うことができません。運用益を最大化したい人にとっては、学資保険よりもNISAやiDeCo、株式投資などの資産運用の方が適している場合があります。
例えば、Cさんは学資保険ではなく、つみたてNISAを活用して毎月積立投資を行いました。その結果、10年間で資産を大きく増やすことができ、大学進学時に十分な資金を用意できました。
学資保険をおすすめする人の特徴
計画的に教育資金を準備したい
教育費を確実に貯めるためには、計画的に積み立てることが重要です。学資保険は強制的に貯蓄を続ける仕組みになっているため、貯金が苦手な人にとって適した選択肢になります。
実例として、Dさんはこれまで貯金をしようと思っても、なかなか続きませんでした。しかし、学資保険に加入したことで、毎月確実に積み立てる習慣がつき、満期時にしっかりとした教育資金を用意できました。
保障を得ながら教育資金を貯めたい
学資保険の「保障型」では、契約者に万が一のことがあった場合でも、残りの保険料の支払いが免除され、満額の保険金を受け取ることができます。そのため、万が一のリスクに備えながら教育資金を準備したい人に向いています。
実例として、Eさんは、学資保険の保障型に加入しました。契約から5年後、予期せぬ病気で亡くなってしまいましたが、保険料の支払いは免除され、満期時には予定通りの保険金が支払われました。
学資保険の選び方・比較ポイント

返戻率をチェック!貯蓄型を選ぶなら重要
学資保険を選ぶ際には、返戻率が高いものを選ぶことが重要です。返戻率とは、支払った保険料に対して受け取れる保険金の割合を示すもので、100%以上であれば、支払額以上の金額を受け取れることになります。
返戻率の比較例
・A社:返戻率110%、貯蓄型で高返戻率
・B社:105%、保障型でバランスが良い
・C社:98%、保障重視で手厚い
例えば、Fさんは返戻率110%の学資保険に加入し、支払総額200万円に対して220万円を受け取ることができました。
満期保険金の受取方法(分割 vs 一括)
学資保険の満期保険金の受取方法には「一括受取」と「分割受取」の2種類があります。
・一括受取:大学入学時にまとまった金額を受け取れる
・分割受取:高校・大学入学時など、段階的に保険金を受け取れる
実例として、Gさんは分割受取タイプを選び、高校入学時に50万円、大学入学時に150万円を受け取り、教育費の負担を分散させました。
保険料の支払い期間と負担を確認
学資保険の保険料の支払い方法には、短期払い(10年払込など)と長期払い(18歳まで払い続ける)があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
短期払い
・メリット:返戻率が高くなる
・デメリット:月々の負担が大きい
長期払い
・メリット:月々の負担が少ない
・デメリット:返戻率が低くなる
実例として、Hさんは月々の負担を減らしたいと考え、18歳まで保険料を払うプランを選びました。一方、Iさんは早く支払いを終えたいと考え、10年間の短期払いを選びました。
保険会社の信頼性・評判を調べる
学資保険を契約する際には、保険会社の信頼性や評判を事前に確認することが重要です。倒産リスクが低く、顧客満足度が高い会社を選ぶことで、安心して長期契約を結ぶことができます。
確認すべきポイント
・保険会社の経営状況(ソルベンシー・マージン比率)
・契約者の口コミや評判
・返戻率の実績
実例として、Jさんは評判の良い保険会社を比較し、過去の支払実績や口コミを調査したうえで、信頼性の高い会社を選びました。
学資保険を選ぶ際には返戻率、受取方法、保険料の負担、保険会社の信頼性を総合的に考慮することが大切です。
返戻率が高いおすすめの学資保険ランキング

学資保険を選ぶ際に最も重視されるポイントの一つが「返戻率」です。返戻率とは、支払った保険料に対して、どれだけの満期保険金を受け取れるかを示す数値です。返戻率が100%を超えると、支払った金額以上の保険金を受け取れることになります。
学資保険のランキングのポイントは、まとめると以下のようになります。
・返戻率が高い保険ほど、支払った金額よりも多くの保険金を受け取れる
・早く加入するほど返戻率が上がる傾向がある
・一括払い・短期払いを選択すると返戻率が向上する
第1位:ソニー生命(学資金準備スクエア)
ソニー生命の「学資金準備スクエア」は、返戻率の高さと柔軟なプラン設計が魅力です。契約者の希望に応じて受取方法を選択できるため、教育費の支出時期に合わせてプランを調整可能です。
特徴
・返戻率は約105~110%と高水準
・受取タイミングをカスタマイズできる
・保険料払込期間が短いほど返戻率が向上
第2位:フコク生命(みらいのつばさ)
フコク生命の「みらいのつばさ」は、一括受取型のプランが魅力で、高い返戻率を実現できます。
特徴
・返戻率約103~108%
・満期保険金を大学入学時にまとめて受け取れる
・長期払いよりも短期払いの方が返戻率が高い
第3位:明治安田生命(つみたて学資)
大手保険会社の安心感がある「つみたて学資」。保障と貯蓄のバランスが良い点が評価されています。
特徴
・返戻率約102~107%
・保障型の要素も含まれたバランス型
・大手保険会社の安定感
第4位:日本生命(ニッセイ学資保険)
日本生命の「ニッセイ学資保険」は、貯蓄型と保障型の2タイプがあり、目的に応じて選べる点が特徴です。
特徴
・返戻率約101~106%
・分割受取と一括受取を選べる
・保障機能をつけることも可能
第5位:住友生命(スミセイのこどもすくすく保険)
住友生命の「スミセイのこどもすくすく保険」は、特に一括払い時の返戻率が高くなる傾向があります。
特徴
・返戻率約100~105%
・長期払いよりも一括払いや短期払いの方が有利
・保障と貯蓄のバランスを考慮したプラン
口コミ・満足度ランキングで学資保険を比較

学資保険を選ぶ際には、実際に契約した人の口コミや満足度も重要な判断材料になります。
東京海上日動あんしん生命
東京海上日動あんしん生命の学資保険は、顧客対応や手続きのスムーズさが評価されています。
口コミ
「契約手続きがスムーズで、担当者の対応がとても親切だった。」(30代・女性)
ソニー生命
ソニー生命は、返戻率の高さとプランの自由度が評価され、口コミでの満足度が高いです。
口コミ
「返戻率が高く、満期時にしっかりと資金を受け取ることができた。」(40代・男性)
アフラック
アフラックの学資保険は、保障型プランが充実しており、契約者の安心感を得られる点が特徴です。
口コミ
「万が一の保障がしっかりしているので、安心して契約できた。」(30代・女性)
明治安田生命
明治安田生命は、大手保険会社の信頼性と安定感で人気があります。
口コミ
「長く続く会社だから安心して加入できた。」(50代・男性)
富国生命
富国生命は、貯蓄型と保障型のバランスが良く、特に返戻率を重視する人に選ばれています。
口コミ
「しっかり貯められて、受け取り時に想定よりも多くの金額を受け取れた。」(40代・女性)
学資保険は、返戻率の高さだけでなく、顧客満足度や手続きのスムーズさも考慮して選ぶことが重要です。ランキングを参考に、自分に合ったプランを選んでください。
学資保険の返戻率を高くするコツ

学資保険を選ぶ際、できるだけ高い返戻率の商品を選びたいと考える方が多いでしょう。返戻率を上げるためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。以下の4つの方法を実践することで、より多くの保険金を受け取ることが可能になります。
早めに契約する(子どもが生まれた直後がベスト)
学資保険は、子どもが生まれた直後に契約するのが最も有利です。年齢が若いうちに加入すると、支払期間が長く設定できるため、保険料が抑えられ、結果的に返戻率が向上します。また、早期加入により契約時の金利が高くなるケースもあります。
実例として、Aさんは子どもが生後3カ月のタイミングで学資保険に加入。10年払いで契約し、返戻率108%のプランを選択しました。一方、Bさんは子どもが5歳になってから加入しましたが、返戻率は102%に低下していました。
払込期間を短くする
学資保険では、保険料の払い込み期間が短いほど返戻率が高くなる傾向があります。10年払いや15年払いなどの短期払込を選択することで、支払総額を抑えつつ、高い返戻率を確保することが可能です。
10年払い
・返戻率の目安:約108%
・返戻率が最も高いが、月々の負担が大きい
15年払い
・返戻率の目安:約105%
・バランスが良く、多くの人が選択する
18年払い
・返戻率の目安:約102%
・月々の負担は軽いが、返戻率が下がる
実例として、Cさんは負担は大きいものの「10年払い」を選択し、返戻率110%のプランを契約。最終的に、支払総額よりも多くの保険金を受け取ることができました。
年払いにする
学資保険は、毎月の支払いではなく、年払いを選択することで保険料の割引が適用され、返戻率が向上します。これは、保険会社が一括で資金を運用できるため、その分のコストが削減されるためです。
実例として、Dさんは毎月払いのプランでは返戻率105%でしたが、年払いに変更したことで返戻率が107%に上昇しました。
余計な特約を外す
学資保険には、医療保障や災害保障などの特約を追加できる場合があります。しかし、これらの特約を付けると保険料が上がるため、結果的に返戻率が低下してしまいます。教育資金を貯める目的で加入する場合は、特約なしのシンプルなプランを選ぶことが大切です。
実例として、Eさんは死亡保障付きのプランを検討していましたが、特約を外すことで返戻率が103%から108%に上昇しました。
学資保険以外の教育資金の準備方法

学資保険は教育資金を準備するための方法の一つですが、その他の方法を併用することで、より効果的に資金を貯めることができます。以下では、学資保険以外の代表的な教育資金準備の方法について解説します。
児童手当を活用する
児童手当は、子どもが生まれてから中学卒業までの間、国から支給される手当です。支給額をそのまま貯蓄することで、学資保険に匹敵する金額を準備することができます。
以下に2024年時点の児童手当の支給額を挙げていきます。
0~3歳
・月額支給額:15,000円
・受取総額(15歳まで):約54万円
3~小学校卒業
・月額支給額:10,000円(第1・2子)/15,000円(第3子以降)
・受取総額(15歳まで):約84万円
中学生
・月額支給額:10,000円
・受取総額(15歳まで):約36万円
実例として、Fさんは児童手当を全額貯蓄し、高校進学時には約180万円の資金を確保することができました。
財形貯蓄で計画的に貯める
財形貯蓄は、企業に勤める人が給与から天引きで積み立てることができる貯蓄制度です。自動的に積み立てができるため、無理なく教育資金を準備できます。
財形貯蓄のメリット
・給与天引きのため、確実に貯蓄できる
・利息が非課税(一定の条件あり)
・目的別に貯蓄できる(一般財形・住宅財形・年金財形)
実例として、Gさんは毎月2万円を財形貯蓄に回し、10年間で240万円の教育資金を準備しました。
NISAで資産運用しながら準備する
NISA(少額投資非課税制度)を活用して、教育資金を運用する方法もあります。NISAは、一定額までの投資利益が非課税となるため、長期的に資産を増やすのに適しています。
つみたてNISAの特徴
・年間40万円までの投資額が非課税
・最長20年間の非課税運用が可能
・投資信託を中心とした運用でリスク分散できる
例えば、HさんはつみたてNISAを活用して毎月3万円を積み立て、15年後には約700万円の資産を形成することに成功しました。
低解約返戻金型終身保険を活用
低解約返戻金型終身保険は、一定期間解約すると返戻金が少なくなる代わりに、満期時の返戻率が高くなる保険です。学資保険と同様に資産を貯める手段として活用できます。
低解約返戻金型終身保険のメリット
・長期契約で高い返戻率を期待できる
・解約しなければ元本割れのリスクが少ない
・生命保険の役割も果たせる
実例として、Iさんは低解約返戻金型終身保険を利用して毎月2万円ずつ積み立て、18年後に返戻率120%の保険金を受け取りました。
教育資金を準備する方法は、学資保険だけではありません。児童手当や財形貯蓄、NISA、終身保険などを活用することで、より効果的に資産を増やすことができます。自分に合った方法を組み合わせ、計画的に教育資金を準備しましょう。
学資保険の手続きと注意点

学資保険は長期間にわたる契約となるため、加入前のチェックや契約後の見直しが重要です。また、生命保険料控除の適用範囲について理解しておくことで、節税効果を最大限に活かせます。以下に、学資保険の手続きと注意点について詳しく解説します。
加入前に確認すべきポイント
学資保険に加入する前に、以下のポイントを確認しておくことが大切です。
1.返戻率の確認
・返戻率が100%を超える商品を選ぶことで、払った金額よりも多くの保険金を受け取れる。
・返戻率が高いほど貯蓄効果が大きいが、保障が少なくなるケースもある。
2.払込期間と受取方法の選択
・払込期間が短いほど返戻率は高くなるが、月々の負担は大きくなる。
・一括受取と分割受取の違いを理解し、自分のライフプランに合った方法を選ぶ。
3.保険会社の信頼性と口コミ
・会社の経営状況や支払い実績をチェックする(ソルベンシー・マージン比率など)。
・実際に利用した人の口コミや満足度を参考にする。
4.特約の有無
・不要な特約をつけると保険料が上がり、返戻率が下がる。
・保障が必要な場合は、別途生命保険や医療保険でカバーすることを検討。
実例として、Aさんは加入前に複数の学資保険を比較し、最も返戻率の高いプランを選択。結果的に、払い込んだ保険料の108%を満期時に受け取ることができました。
契約後の見直し・変更のポイント
学資保険を契約した後でも、状況の変化に応じて見直しが必要になる場合があります。
1.ライフステージの変化に対応する
・家計の状況が変わった場合、払い込み期間の変更や特約の見直しを検討。
・収入が増えた場合は短期払いに変更することで、返戻率を向上させることも可能。
2.中途解約のリスクを理解する
・学資保険は途中解約すると元本割れすることが多いため、緊急時以外は解約を避ける。
・もし解約が必要な場合は、返戻率を考慮しながら最適なタイミングを見極める。
3.契約内容の変更手続き
・受取人の変更や受取方法の変更が可能か、契約時に確認しておく。
・保険料支払いの方法(年払い・月払い)の変更についても検討する。
例えば、Bさんは契約後に収入が増えたため、当初の「18歳払い」を「10年払い」に変更。結果的に返戻率が向上し、より多くの保険金を受け取ることができました。
生命保険料控除の適用範囲
学資保険の保険料は、「生命保険料控除」の対象となるため、一定の税制優遇を受けることができます。
生命保険料控除の概要
・一般生命保険料控除:控除限度額(年間)最大4万円
・旧制度(2011年以前契約):最大5万円
・どちらも年末調整・確定申告が必要
控除を受けるためのポイント
・保険会社から発行される「生命保険料控除証明書」を提出する必要がある。
・会社員の場合は年末調整、自営業者の場合は確定申告で控除申請を行う。
・控除額は、支払った保険料によって異なるため、契約時に確認しておく。
実例として、Cさんは学資保険の年間保険料が10万円だったため、4万円の控除を受けることができ、所得税と住民税の負担を軽減しました。
学資保険に関するよくある質問

学資保険の代わりに教育資金を貯める方法は?
学資保険以外にも、教育資金を貯める方法はいくつかあります。
1.つみたてNISA
・年間40万円まで非課税で運用可能。
・長期投資による資産形成に適している。
2.財形貯蓄
・給与天引きで確実に貯蓄できる。
・目的別に積み立てることが可能。
3.定期預金・積立貯金
・元本保証があり、安全に資金を確保できる。
・金利は低いが、リスクを抑えた貯蓄が可能。
例えば、Dさんは学資保険ではなくつみたてNISAを活用し、15年後には約500万円の教育資金を準備することができました。
返戻率120%の学資保険はある?
現在、日本国内の学資保険で返戻率120%を超える商品はほとんどありません。高返戻率の商品は、低金利環境の影響で販売が難しくなっているためです。
代替案
・外貨建て保険:為替リスクはあるが、高返戻率が期待できる。
・低解約返戻金型終身保険:長期間の運用で高い返戻率が可能。
実例では、Eさんは日本円建ての学資保険ではなく、外貨建ての終身保険を利用。結果的に20年後には返戻率125%の保険金を受け取ることができました。
中学生から加入しても間に合う?
中学生から学資保険に加入することは可能ですが、返戻率が低くなるため、あまりおすすめできません。
遅めに加入する場合のデメリット
・払込期間が短くなるため、月々の保険料が高額になる。
・返戻率が低くなり、貯蓄型としてのメリットが減る。
・早期に解約すると元本割れのリスクが高まる。
代替案
・つみたてNISAで教育資金を運用する。
・定期預金や積立貯金で資金を確保する。
例えば、Fさんは子どもが中学生のタイミングで学資保険の加入を検討しましたが、返戻率が低いため、代わりに短期の定期預金とつみたてNISAを組み合わせて資産形成を行いました。
学資保険の手続きや注意点を理解し、必要に応じて代替手段を活用することで、より効率的に教育資金を準備できます。自分のライフスタイルや経済状況に合わせて、最適な方法を選択しましょう。
学資保険を賢く選んで、確実に教育資金を準備しよう

学資保険は、計画的に教育資金を準備できる有効な手段です。返戻率の高い商品を選び、無駄な特約を外すことで、より効率的に資産を増やすことができます。また、NISAや財形貯蓄など他の貯蓄方法と組み合わせることで、より柔軟な資金計画を立てることが可能です。
本記事では、学資保険の基本から選び方、おすすめ商品、さらに返戻率を上げるコツまで詳しく解説しました。お子さまの将来のために、最適な学資保険を選んで安心できる教育資金の準備を始めましょう。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 お知らせ2025年5月16日保険の特約とは?初心者向け解説
お知らせ2025年5月16日保険の特約とは?初心者向け解説 お知らせ2025年5月16日学資保険おすすめランキングと選び方【初心者向けガイド】
お知らせ2025年5月16日学資保険おすすめランキングと選び方【初心者向けガイド】 マインド2025年5月16日自転車のヘルメット着用ガイド|法律・背景・選び方
マインド2025年5月16日自転車のヘルメット着用ガイド|法律・背景・選び方 マインド2025年5月16日自転車の「ながらスマホ」罰則強化と道路交通法改正【2024年11月施行】
マインド2025年5月16日自転車の「ながらスマホ」罰則強化と道路交通法改正【2024年11月施行】


