ガソリン税と暫定税率とは?初心者向けにわかりやすく解説
「ガソリンの暫定税率って結局どういう仕組み?」
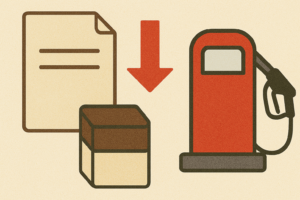
「廃止されたらガソリン価格はどれくらい下がるの?」
こんな疑問を解決します。
本記事では、ガソリン税や暫定税率の基本を初心者向けにわかりやすく解説し、さらに暫定税率が廃止された場合の影響やガソリン価格の変動について詳しく説明します。税金の仕組みがわかれば、今後のガソリン代がどうなるのか、自分の生活にどう影響するのかを理解できます。
実際に、ガソリン税の内訳や暫定税率の歴史を知ることで、燃料費の高騰の理由や今後の政策の動向を予測しやすくなります。本記事を読めば「なぜガソリンが高いのか」「暫定税率が廃止されるとどうなるのか」といった疑問がスッキリ解消されるはずです。
5分で読める内容なので、ガソリン税や暫定税率について理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。ガソリン税とは
ガソリン税は、日本においてガソリンを購入する際に課される税金です。この税金は、道路の整備や維持管理を目的として導入されました。では、このガソリン税はどのような経緯で生まれ、現在どのように使われているのでしょうか。
ガソリン税の導入経緯
ガソリン税は、1950年に「揮発油税」として導入されました。当時、日本は戦後復興の最中で、道路整備が急務でした。そのため、道路建設や維持管理の財源を確保する目的で、この税金が設けられたのです。
その後、1974年には地方自治体の財源を確保するため「地方揮発油税」が新設されました。このように、ガソリン税は時代のニーズに合わせて変更されてきました。
揮発油税と地方揮発油税の違い
ガソリン税には、大きく分けて以下の2つの税金が含まれています。
・揮発油税:国が徴収する税金で、道路整備などに使われる
・地方揮発油税:地方自治体が徴収する税金で、各地域の道路維持管理に使われる
揮発油税は国の財源として使われるのに対し、地方揮発油税は各都道府県の財源となります。つまり、ガソリンを購入するたびに国と地方の両方に税金を納めているのです。
ガソリン税の税額と使用目的
現在のガソリン税は、以下のような税率で設定されています。(※2024年時点)
・揮発油税:48.6円
・地方揮発油税:5.2円
→合計:53.8円
この税収は、主に道路の整備や維持管理に使われています。しかし、近年では一般財源化が進み、必ずしも道路整備だけに使われているわけではありません。
暫定税率とは

暫定税率の歴史
暫定税率は、1974年のオイルショックをきっかけに導入されました。当時、日本は急速な経済成長に伴い、道路インフラの整備が急務でした。しかし、原油価格の高騰によってガソリン価格が上昇し、道路整備のための財源確保が課題となりました。
そのため、ガソリン税に「暫定的な税率」を上乗せする形で暫定税率が導入されたのです。本来、一時的な措置として設けられたこの税率は、その後何度も延長され、現在も維持されています。
暫定税率の撤廃と特例税率
暫定税率は何度も議論の対象となり、2008年には一時的に廃止されたこともあります。しかし、その後すぐに復活し、現在も適用され続けています。
現在のガソリン税のうち、暫定税率部分は以下の通りです。
揮発油税
・本則税率(1Lあたり):24.3円
・暫定税率部分(1Lあたり):24.3円
→合計:48.6円
地方揮発油税
・本則税率(1Lあたり):2.6円
・暫定税率部分(1Lあたり):2.6円
→合計:5.2円
もし暫定税率が完全に廃止されれば、ガソリン価格は1リットルあたり約25円ほど安くなる可能性があります。
ガソリン価格の仕組み
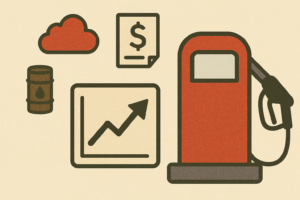
ガソリン価格は、単純に原油価格だけで決まるわけではありません。税金が大きく関わっており、さらに世界的な原油市場の影響も受けています。
ガソリン価格の内訳(本体価格+税金)
ガソリン価格の内訳は、主に以下の3つの要素で構成されています。
1.本体価格(原油価格+精製・流通コスト)
2.税金(揮発油税・地方揮発油税・石油税・消費税)
3.市場要因(為替レート・国際的な原油価格の変動)
ガソリン税は固定額ですが、原油価格の変動によって全体の価格が大きく変わることがあります。
石油諸税とは?ガソリン税以外の税金について
ガソリン価格には、ガソリン税以外にも以下のような税金が含まれています。
・石油税:税率(1Lあたり)約2.8円
・温暖化対策税:約0.76円
・消費税:本体価格+すべての税金に対して10%
特に消費税は、ガソリン税を含めた金額に対して課されるため、いわゆる「二重課税」として問題視されることもあります。
ガソリンにかかる消費税の課税の仕組み
消費税は、ガソリン本体価格だけでなく、揮発油税や地方揮発油税などの税金を含んだ価格に対して課税されます。つまり、税金に税金がかかる「二重課税」の構造になっているのです。
例えば、1リットルあたりのガソリン価格が160円の場合、消費税の計算は以下のようになります。
1.ガソリン本体価格:100円
2.ガソリン税(揮発油税+地方揮発油税):53.8円
3.石油税・温暖化対策税:3.56円
4.消費税(10%):(100+53.8+3.56)×10% = 15.74円
5.最終価格:約160円
このように、ガソリン価格には多くの税金が含まれているため、価格が高騰しやすい仕組みになっています。
暫定税率の廃止が与える影響

ガソリンの価格を大きく左右する「暫定税率」。この税率が廃止されれば、ガソリン価格が大幅に下がる可能性がありますが、実際にはどのような影響があるのでしょうか。ここでは、暫定税率の廃止時期、ガソリン価格への影響、そして税金の変化について詳しく解説します。
暫定税率廃止はいつから?
暫定税率の廃止は、これまで何度も議論されてきました。特に、2008年には一時的に廃止され、ガソリン価格が大きく変動したことがあります。しかし、その後すぐに復活し、現在も継続されています。
現在、暫定税率の廃止について具体的な決定はなされていませんが、以下の要因が今後の議論のポイントとなります。
1.政府の税収確保の問題
2.原油価格の変動とエネルギー政策
3.消費者負担の軽減
また、暫定税率の代わりに導入される可能性がある「環境税」や「カーボンプライシング」などの新たな税制の動向も、廃止の時期を左右する要因となるでしょう。
暫定税率が廃止されたらガソリン価格はいくらになる?
現在のガソリン税のうち、暫定税率部分は以下の通りです。
揮発油税
・本則税率(1Lあたり):24.3円
・暫定税率部分(1Lあたり):24.3円
→合計:48.6円
地方揮発油税
・本則税率(1Lあたり):2.6円
・暫定税率部分(1Lあたり):2.6円
→合計:5.2円
計
・本則税率(1Lあたり):26.9円
・暫定税率部分(1Lあたり):26.9円
→合計:53.8円
仮に暫定税率が完全に廃止された場合、ガソリン1リットルあたり約27円程度の値下げが期待できます。ただし、これに消費税の影響を考慮すると、実際の値下げ幅はそれよりも若干少なくなる可能性があります。
例えば、現在のガソリン価格が 160円/L の場合、暫定税率が撤廃されることで、価格は 133円/L 程度まで下がる可能性があります(※原油価格や流通コストの変動を除く)。
1リットル当たりの石油諸税および消費税の変化
ガソリン価格には、ガソリン税(揮発油税+地方揮発油税)以外にも、さまざまな税金が含まれています。
揮発油税
・変更前(暫定税率あり):48.6円
・変更後(暫定税率廃止):24.3円
地方揮発油税
・変更前(暫定税率あり):5.2円
・変更後(暫定税率廃止):2.6円
石油税
・変更前(暫定税率あり):2.8円
・変更後(暫定税率廃止):2.8円
温暖化対策税
・変更前(暫定税率あり):0.76円
・変更後(暫定税率廃止):0.76円
消費税(10%)
・変更前(暫定税率あり):約16円(160円/L時)
・変更後(暫定税率廃止):約13円(133円/L時)
合計
・変更前(暫定税率あり):73.36円
・変更後(暫定税率廃止):43.46円
このように、暫定税率の廃止によってガソリン価格は大きく下がりますが、一方で政府の税収が減るため、新たな課税方法が検討される可能性があります。
暫定税率廃止によるメリット・デメリット

暫定税率が廃止されると、多くの人がガソリン価格の低下を歓迎するでしょう。しかし、一方で財源の確保や経済全体への影響も考えなければなりません。ここでは、メリットとデメリットを整理して解説します。
消費者の負担軽減
メリット
・ガソリン価格が下がることで、家計の負担が軽減される
・自家用車を多く利用する人にとって、毎月のガソリン代が削減できる
・公共交通機関のコストも減少し、運賃の値下げにつながる可能性がある
例えば、1リットルあたり27円の値下げが実現すると、50リットル給油する場合、1回の給油で1,350円の節約になります。年間に換算すると、大きな金額になります。
物流コストの削減
メリット
・トラック輸送のコストが下がるため、商品の流通コストが減少する
・配送料のコストが下がることで、消費者の負担も軽減される可能性がある
・企業のコスト削減によって、経済全体の活性化が期待できる
物流業界では、燃料費がコストの大きな割合を占めています。例えば、1台のトラックが1か月に1,500リットルの燃料を消費すると、暫定税率の廃止により、1台あたり年間約50万円のコスト削減が見込めます。
財源の確保とその課題
デメリット
・ガソリン税の収入減少により、道路整備の予算が不足する可能性がある
・一般財源化されているため、教育・福祉・医療分野にも影響を与える可能性がある
・政府が新たな税制(例:環境税、走行距離課税)を導入する可能性がある
廃止と再開
2008年に暫定税率が一時廃止された際、ガソリン価格は下がりましたが、財源確保の問題が浮上し、その後すぐに復活しました。
原油価格依存のリスク
デメリット
・税金が下がることで、原油価格の変動がガソリン価格に直接影響する
・暫定税率があることで価格をある程度安定させていたが、それがなくなることで価格の乱高下が発生する可能性がある
もし原油価格が急騰した場合、ガソリン税の調整がないため、価格が一気に跳ね上がるリスクがあります。例えば、2022年のロシア・ウクライナ情勢による原油価格高騰の際、ガソリン価格が 1リットルあたり200円を超えたことがありました。
暫定税率の廃止によって、消費者や企業にとってはメリットが多いものの、一方で政府の税収減少や価格の変動リスクといったデメリットもあります。今後の政策次第では、新たな税制が導入される可能性もあるため、引き続き動向を注視する必要があります。
ガソリン補助金の影響

ガソリン価格の高騰を抑えるために政府が行っている「ガソリン補助金」。しかし、補助金は永続的な制度ではなく、将来的には廃止される可能性があります。ここでは、ガソリン補助金の仕組みと、廃止された場合のユーザーへの影響について解説します。
ガソリン補助金とは?
ガソリン補助金とは、政府がガソリン価格の急騰を抑えるために、石油元売会社(製油所やガソリンスタンドの供給元)に支給する補助金です。これにより、小売価格の上昇を抑え、消費者の負担を軽減することを目的としています。
制度の概要
・正式名称:燃料油価格激変緩和対策事業
・開始時期:2022年1月(原油高騰対策として導入)
・補助の仕組み:一定の基準価格を超えた場合、超過分の一部を政府が負担
・対象:ガソリン、軽油、灯油、重油など
補助金の適用により、2023年には 1リットルあたり10円〜30円程度の価格抑制が行われていました。
ガソリン補助金廃止でユーザーの負担はどれくらい増えるのか
補助金が廃止されると、ガソリン価格は市場の原油価格や税金の影響を直接受けるようになり、消費者の負担が増加します。
影響の試算
例えば、2023年時点で補助金によって 1リットルあたり20円程度の価格抑制が行われていた場合、補助金廃止後には以下のような影響が考えられます。
・補助金あり(2023年時点):ガソリン価格(1Lあたり)160円
・補助金廃止後:180円
具体的な影響
・自家用車を利用する家庭では、毎月のガソリン代が増加
・物流コストが上がり、食品や日用品の価格にも影響
・地方の交通機関(バス・タクシーなど)の運賃が値上がりする可能性
政府は補助金の段階的縮小を検討していますが、その代わりとなる対策が不十分な場合、家計への負担が大きくなることが懸念されます。
ガソリン税の今後と課題

ガソリン税は、日本の税収の重要な部分を占めていますが、その課税方法にはさまざまな課題があります。今後の政策によっては、ガソリン価格や消費者の負担が大きく変わる可能性があります。
トリガー条項とは?発動条件と影響
トリガー条項とは
ガソリン価格が一定の基準を超えた場合に、揮発油税の暫定税率を停止する制度のことです。これにより、価格高騰時に消費者の負担を軽減することを目的としています。
発動条件
・全国平均のレギュラーガソリン価格が3か月連続で160円を超えた場合
・その後、ガソリン税の一部(暫定税率)が自動的に停止
トリガー条項が発動すると
・ガソリン価格が1リットルあたり約25円下がる
・消費者の負担が軽減される
・政府の税収が減少し、財政に影響を与える
しかし、東日本大震災後の復興財源確保のため、トリガー条項は2011年から凍結されており、現在は発動されていません。解除されるかどうかは、今後の政府の方針次第です。
日本のガソリン価格高騰の背景
ガソリン価格の高騰には、さまざまな要因が関係しています。ここでは、国際的な要因と国内の要因に分けて解説します。
国際的背景
1.原油価格の高騰:OPEC(石油輸出国機構)の減産政策、ロシア・ウクライナ情勢による供給不安、世界的なエネルギー需要の増加
2.為替レートの影響:日本は原油をほぼ100%輸入に依存、また円安になると輸入コストが上がり、ガソリン価格も上昇
国内の背景
1.ガソリン税の影響:日本のガソリン税は1リットルあたり50円以上と高水準、また税金がガソリン価格の約40%を占めるため、価格が下がりにくい
2.燃料油価格激変緩和補助金の縮小:補助金が減少すると、価格が上昇しやすくなる
ガソリンの“二重課税”は理不尽?税制改正の議論
日本のガソリン税の課税方法には、「二重課税」と呼ばれる問題があります。
二重課税とは?
・ガソリン価格には「ガソリン税(揮発油税+地方揮発油税)」が含まれる
・さらにガソリン税を含めた総額に対して消費税(10%)がかかる
・つまり、税金に対して税金がかかるという構造
具体例
1リットル160円のガソリンの場合、以下のような内訳になります。
・ガソリン本体価格:86円
・ガソリン税(揮発油税+地方揮発油税):53.8円
・石油税・温暖化対策税:3.56円
・消費税(10%):16円(※税金部分にも課税)
→合計:160円
この二重課税の仕組みは、消費者にとって不公平だとする意見が多く、税制改革の議論がたびたび行われています。しかし、ガソリン税の収入は国にとって重要な財源であるため、抜本的な改革には至っていません。
ガソリン税や補助金、暫定税率の問題は、単にガソリンの価格だけでなく、日本の経済全体に影響を与える要素です。特に、ガソリン税の二重課税や補助金の廃止問題は、消費者の負担に直結するため、今後の政策動向を注意深く見守る必要があります。
ガソリン税と暫定税率のポイントをおさらい

今回は、ガソリン税と暫定税率の仕組みや影響について解説しました。
ガソリン価格には、揮発油税や地方揮発油税をはじめとする多くの税金が含まれており、その中でも暫定税率は価格に大きく関与しています。もし暫定税率が廃止されれば、1リットルあたり約25円の値下げが見込めるものの、道路整備の財源確保など新たな課題が生じる可能性があります。
また、ガソリン補助金の縮小や廃止によって、今後の価格動向はさらに不透明です。私たち消費者にとって、ガソリン税制の変化は家計に直接影響する重要な要素です。今後の政策動向を注視しながら、賢く情報を活用していきましょう。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 マインド2025年5月23日花粉症の治療法【初心者向けガイド】
マインド2025年5月23日花粉症の治療法【初心者向けガイド】 マインド2025年5月22日加齢とは何か?
マインド2025年5月22日加齢とは何か? マインド2025年5月22日飲食店の営業許可とは?取得方法から手続きまで徹底解説
マインド2025年5月22日飲食店の営業許可とは?取得方法から手続きまで徹底解説 お知らせ2025年5月21日ガソリン税と暫定税率とは?初心者向けにわかりやすく解説
お知らせ2025年5月21日ガソリン税と暫定税率とは?初心者向けにわかりやすく解説


